平成21(2009)年5月5-6日(火・水)、京都市で周った神社
梶取社 | 貴船神社(本宮) | 貴船神社(奥宮)の船形石 | 貴船神社(奥宮) | 貴船神社(結社)| 鞍馬寺 | 鞍馬寺の不動堂 | 鞍馬寺の魔王殿 |
河合神社 | 下賀茂神社(賀茂御祖神社) | 三井神社(みつい) | 出雲井於神社(いずもいのへ)
| 上賀茂神社(賀茂別雷神社) | 上賀茂神社摂社の片山御子神社 | 神山(こうやま) | 深泥池(ミゾロ池) | 広沢池 |
罔象女宮としての伝承を失った貴船神社の奥宮 トップページ
罔象女宮としての伝承を失った貴船神社の奥宮の本殿


ご祭神
【主祭神】高龗神(たかおかみのかみ)瓊々杵尊は比叡山の造成の次に貴船山の嶺に罔象女神、愛宕山に軻遇突智神
◆大濡煮尊の御世から171万98年経た紀元前1,290,607年に瓊々杵尊は八洲巡りの勅を得、第二次天孫降臨の途中、酒折宮に入った。
そこで葦津姫(あしつひめ)を一夜召されて契(ちぎ)りを結んだ。
翌年の大濡煮尊の御世から171万99年経た紀元前1,290,606年の6月1日に葦津姫(あしつひめ)は三子を生んだ。
瓊々杵尊に疑われた葦津姫(あしつひめ)は、三人の御子を火の中で生んだのだ。
三人の御子は、火に状態に従って
・火明
・火進
・火遠
といわれている。
造成の結果、穀物がたくさん出来るようになったのでミゾロ池(深泥池)と呼ぶようになった。
ミゾロ池西岸の岩を砕き、小石にして川に流しいれ水をあふれさせ、荒地に水を引き、雷(鳴る神)を別け鎮め、葵葉(あおいば)と桂(かつら)によって軻遇突智神(かぐつちのかみ)と罔象女神(みずはめのかみ)をお生みになった。
このことから瓊々杵尊は「別雷(わけいかづち)」という称号を天照神から賜った。
そこで葦津姫(あしつひめ)を一夜召されて契(ちぎ)りを結んだ。
翌年の大濡煮尊の御世から171万99年経た紀元前1,290,606年の6月1日に葦津姫(あしつひめ)は三子を生んだ。
瓊々杵尊に疑われた葦津姫(あしつひめ)は、三人の御子を火の中で生んだのだ。
三人の御子は、火に状態に従って
・火明
・火進
・火遠
といわれている。
◆天之忍穂耳尊が箱根神として神上がられてから、瓊々杵尊は3年の喪祭りを行った。
◆3年の喪祭りを終えてから、瓊々杵尊は比叡山を造成された。造成の結果、穀物がたくさん出来るようになったのでミゾロ池(深泥池)と呼ぶようになった。
ミゾロ池西岸の岩を砕き、小石にして川に流しいれ水をあふれさせ、荒地に水を引き、雷(鳴る神)を別け鎮め、葵葉(あおいば)と桂(かつら)によって軻遇突智神(かぐつちのかみ)と罔象女神(みずはめのかみ)をお生みになった。
このことから瓊々杵尊は「別雷(わけいかづち)」という称号を天照神から賜った。
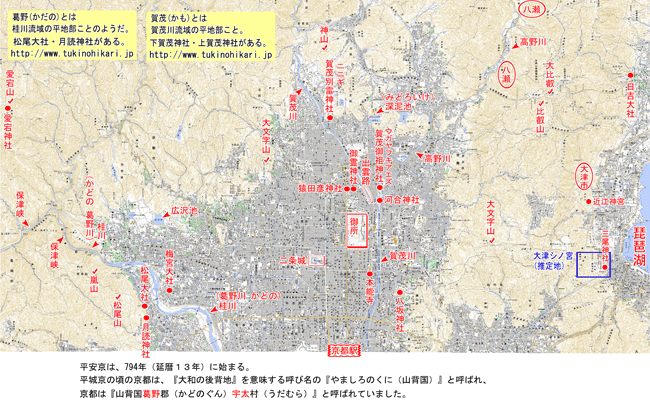
貴船神社の創建は、瓊々杵尊が罔象女神と軻遇突智神を別けたことに由来するのかもしれない。
比叡山の造成 → ミゾロ池 → 葵葉と桂によって罔象女神と軻遇突智神を別ける。『秀真伝(ほつまつたゑ)』御機の二十四「コヱ国原見山の紋」(鳥居礼編著、八幡書店、下巻P27-29 )
| 原治君(はらをきみ) | 伊豆崎宮(ゐづさきみや)に | 瓊々杵尊 |
| 箱根神(はこねかみ) | 三年祭りて | 天之忍穂耳尊を箱根神として。 |
| 瀛壺(おきつぼ)の | 峰より眺(なが)め | 瀛壺とは近江(滋賀県)のこと |
| 勅(みことのり) | 「汝(なんじ)山咋命(やまくひ) | |
| 山背(やまうしろ) | 野お堀り土お | 山背、山城は京都府南部のこと |
| こゝに上げ | 大日(おおひ)の山お | 大日山とは富士山のこと。 |
| 遷(うつ)すべし」 | 一枝(ひとゑだ)に足り | 一枝(ひとゑだ)は60年。 |
| 一枝(ひゑ)の山 | その池水(いけみず) | 比叡山 |
| 田のゾロに | 乗りて稔れば | |
| ミゾロ池 | まゝあり池の | 京都市北区上賀茂狭間町の深泥池(みどろいけ)のこと |
| 西岩屋(にしいわや) | 実(み)食(は)む礫(ゐしな)お | |
| 稜威(ゐつ)別(わ)けて | 流す石川(ゐしかわ) | |
| 塞(せ)き入れて | 荒地(あれわ)お生(い)けて | |
| 鳴る神お | 別(わ)けて鎮(しづ)むる | |
| 軻遇突智神(かぐつち)と | 罔象女神(みづはめ)お生(う)む |
貴船神社を罔象女宮といった。 (PP103-105) 愛宕山の愛宕神社若宮の祭神に、雷神と軻遇突智神がいる。 |
| 葵葉(あおいば)と | 桂(かつら)に伊勢の | |
| 勅(みことのり) | 「天(あめ)は降り照り | |
| 全(まつた)きは | 雷(いかづち)別(わ)けて | |
| 神(かみ)を生(う)む | これ国常立尊(とこたち)の | |
| 新(さら)の稜威(ゐづ) | 別雷(わけいかづち)の | |
| 天君(あまきみ)」と | 璽(をしで)賜(たま)わる | |
| 広沢お | 太田命(おおた)に掘らせ | 京都市右京区嵯峨広沢町に広沢池があるが何らかの関係があるか? |
| 国となす |
彦火々出見尊に産屋を覗かれたことを恥じ、豊玉姫は罔象女宮で恥を忍んだ
◆大濡煮尊の御世から2,102,078年経た紀元前898,627年に瓊々杵尊が火々出見尊へ天位継承され、豊玉姫は鵜葺草葺不合尊を生んでいる。
敦賀湾岸の気比の松原で鵜葺草葺不合尊が誕生した時、彦火々出見尊に産屋を覗かれたことを恥じ、豊玉姫は罔象女宮(貴船神社)に身を隠した。
◆罔象女宮(貴船神社)において瓊々杵尊の説得により、豊玉姫は心を許した。
豊玉姫は、瓊々杵尊が神上がられた喪祭りを罔象女宮(貴船神社)で行い、再び宮中に戻った。
敦賀湾岸の気比の松原で鵜葺草葺不合尊が誕生した時、彦火々出見尊に産屋を覗かれたことを恥じ、豊玉姫は罔象女宮(貴船神社)に身を隠した。
◆罔象女宮(貴船神社)において瓊々杵尊の説得により、豊玉姫は心を許した。
豊玉姫は、瓊々杵尊が神上がられた喪祭りを罔象女宮(貴船神社)で行い、再び宮中に戻った。
『秀真伝(ほつまつたゑ)』御機の二十六「鵜葺草葵桂の紋」(鳥居礼編著、八幡書店、下巻P27-29 )
| 君松原に | 彦火々出見尊。鵜葺草葺不合尊が生まれた敦賀湾岸の気比の松原。 | |
| 涼(すヾ)み来て | 産屋(うぶや)覗(のぞ)けば | |
| 腹這(はらば)ひに | 装(よそ)ひなければ | |
| 枢(とぼそ)引(ひ)く | 音(おと)に寝覚めて | 枢とは開き戸の、かまちの上下の端に突き出た部分。これが回転軸となって戸が開閉する。 |
| 恥(はづ)かしや | 弟(おと)建祗命(たけずみ)と | 建祗命は豊玉姫の弟で、玉依姫神の父。 |
| 六月(みなづき)の | 禊(みそぎ)してのち | |
| 産屋(うぶや)出て | 遠敷(をにふ)に至り | 福井県遠敷郡(おにゅうぐん)。滋賀県と京都府の県境をなす。 |
| 御子(みこ)抱き | 眉目(みめ)見手(みて)撫でて | |
| 「母は今 | 恥(はぢ)帰るなり | |
| 真見(まみ)ゆ折 | もがな」と捨てゝ | |
| 朽木川(くちきかわ) | 上(のぼ)り山超(やまこ)え | 滋賀県高島郡を流れる安曇川の中流を朽木川という。 |
| やゝ三日(みか) | 別雷山(わけつち)の峰(ね)の | 別雷山とは、貴船山のこと。 |
| 罔象女神(みずはめ)の | 社(やしろ)に休(やす)む | 京都市左京区貴船町に鎮座する貴船神社のこと。 |
| = 中略 = | ||
| 明(あく)る年 | 太上(おゝゑ)天皇(すべらぎ) | 皇位を退いた瓊々杵尊 |
| 別雷山(わけつち)の | 葵桂(あおいかつら)お | |
| 袖(そで)に掛(か)け | 宮(みや)に至(いた)れば | |
| 姫(ひめ)迎(むか)ふ | 時に葉(は)お持(も)ち | |
| 「これ如何(いかん)」 | 豊玉姫(とよたま)答え | |
| 「葵葉(あおいば)ぞ」 | 「またこれ如何(いかん)」 | |
| 「桂葉(かつらば)ぞ」 | 「いづれ欠(か)くるや」 | |
| 「まだ欠(か)けず」 | 「汝(なんじ)世(よ)お捨(す)て | |
| 道(みち)欠(か)くや」 | 姫(ひめ)は畏(おそ)れて | |
| = 中略 = | ||
| 姫(ひめ)は恥(はぢ) | 陥(おちい)りいわず | |
| 美穂津姫(みほつひめ) | 行幸(みゆき)送りて | 奇彦命(奇杵命の子)の妻で子守神の母 |
| こゝにあり | 問えば喜び | |
| 答え問う | 美穂津姫(みほつ)諾(うなづ)き | |
| 「太上(おゝゑ)君(きみ) | 心(こころ)な痛(いた)め | |
| 給(たま)ひぞよ | 君(きみ)と姫(ひめ)とは | |
| 日と月と | 睦(むつ)まじなさん」 | |
| 申すとき | 大君(おゝきみ)笑(ゑ)みて | |
| 建祗命(たけづみ)に | 豊玉姫(とよたま)養(た)せと | |
| 川合(かわあい)の | 国(くに)賜(たま)わりて | 賀茂御祖神社(下賀茂神社)の南側に河合神社(祭神:玉依姫神)が鎮座する。 |
| 谷(たに)お出(で)て | 室津(むろつ)に亀船(かめ)の | |
| 迎(む)い待つ | 門出(かどい)で送(おく)り | |
| 行幸(みゆき)なす | 君(きみ)ゑ大君(ををきみ) | 彦火々出見尊に瓊々杵尊が。 |
| 遺(のこ)し言(ごと) | 遺言を残す。 | |
| = 中略 = | ||
| 豊玉姫(とよたま)は | 別雷山(わけつちやま)に | 貴船山で邇々杵尊の喪祭りを行う。 |
| 喪(も)は四十八日(よそや) | 年(とし)の祭(まつ)りも | |
| 御饗(みあえ)なす | この後に豊玉姫は再び宮入。 |
彦火々出見尊の亡骸は気比神宮に、豊玉姫の亡骸は罔象女宮に納められる。
◆大濡煮尊の御世から251万1千60年経た紀元前489,645年に火々出見尊と豊玉姫は大津シノ宮で神上がられた。
火々出見尊の御尊骸は、鹽土老翁神に笥飯(けゐ-弁当箱)をもらってから、巡りが開け、鉤(ち)を得る門出(かどで)になった笥飯(けゐ)に納められた。
(※)笥飯神宮の【土公】が御尊骸を納めた場所だろう。
豊玉姫の御尊骸は、罔象女宮(貴船神社)に納められた。
(※)貴船神社奥宮の【船形石(ふながたいわ)】が御尊骸を納めた場所だろう。
敦賀湾岸の気比の松原で鵜葺草葺不合尊が誕生した時、彦火々出見尊に産屋を覗かれたことを恥じ、豊玉姫は罔象女宮(貴船神社)に身を隠したことがあった。
神上がられる直前の瓊々杵尊が罔象女宮(貴船神社)に出向き説得されたことにより、豊玉姫は心を許した。
豊玉姫は、瓊々杵尊が神上がられた喪祭りを罔象女宮(貴船神社)で行い、再び宮中に戻られたのだった。
そいう由縁により、豊玉姫の御尊骸は、罔象女宮(貴船神社)に納められた。
◆玉依姫が神武天皇を身ごもったとき、黄色い船で参拝にきたと伝えられる。
火々出見尊の御尊骸は、鹽土老翁神に笥飯(けゐ-弁当箱)をもらってから、巡りが開け、鉤(ち)を得る門出(かどで)になった笥飯(けゐ)に納められた。
(※)笥飯神宮の【土公】が御尊骸を納めた場所だろう。
豊玉姫の御尊骸は、罔象女宮(貴船神社)に納められた。
(※)貴船神社奥宮の【船形石(ふながたいわ)】が御尊骸を納めた場所だろう。
敦賀湾岸の気比の松原で鵜葺草葺不合尊が誕生した時、彦火々出見尊に産屋を覗かれたことを恥じ、豊玉姫は罔象女宮(貴船神社)に身を隠したことがあった。
神上がられる直前の瓊々杵尊が罔象女宮(貴船神社)に出向き説得されたことにより、豊玉姫は心を許した。
豊玉姫は、瓊々杵尊が神上がられた喪祭りを罔象女宮(貴船神社)で行い、再び宮中に戻られたのだった。
そいう由縁により、豊玉姫の御尊骸は、罔象女宮(貴船神社)に納められた。
◆玉依姫が神武天皇を身ごもったとき、黄色い船で参拝にきたと伝えられる。
『秀真伝(ほつまつたゑ)』御機の二十七「御祖神船魂の紋」(鳥居礼編著、八幡書店、下巻P132-133 )
| 天君(あまきみ)と | 后(きさき)諸(もろ)とも | 彦火々出見尊と豊玉姫。 |
| シノ宮に | 降(お)り居(ゐ)てこゝに |
近江国(滋賀県)大津シノ宮で神上がる。 近くに彦火々出見尊を祀る天孫神社と豊玉姫神を祀る関蝉丸神社(下社)がある。 |
| 神となる | 時四十二鈴 |
大濡煮尊の御世より、251万1千60年。 紀元前489,645年 |
| 八百五十枝(やもゐそゑ) | 極年(きわとし)ネウト | 「極年」は「キアヱ」歴の最後の年という意味。 |
| 八月四日(はつきよか) | 君(きみ)の喪祭(もまつ)り | |
| 四十八日(よそや)済(す)み | 勅(みこと)に任(まか)せ | |
| おもむろお | 伊奢沙別宮(いさゝわけみや) | 福井県敦賀市曙町の気比神宮。古くは「笥飯宮」「笥飯大神宮」と称した。 |
| 笥飯(けゐ)の神 | ゆえは翁(をきな)に | 笥飯(けゐ)とは弁当のこと |
| 笥飯(けゐ)お得(ゑ)て | 巡(めぐ)り開(ひら)ける | |
| 鉤(ち)お得(ゑ)たり | 門出(かどで)の笥飯(けゐ)ぞ | |
| 拍手葉(かしはでは) | 姫はおもむろ | 豊玉姫の亡骸は |
| 罔象女宮(みずはや) | 昔(むかし)渚(なぎさ)に | 罔象女宮(貴船神社) |
| 誓(ちか)いして | ミゾロの竜(たつ)の | |
| 御魂(みたま)得(ゑ)て | 名(な)も相(あゐ)ゾロの | |
| 神(かみ)となる | 田水(たみづ)お守(まも)り | |
| 船(ふね)お生(う)む | 貴船(きぶね)の神は | |
| 船魂(ふなたま)か | 貴船の神は、船魂神 |
豊玉姫の御尊骸を納めた可能性がある船形石(ふながたいわ)
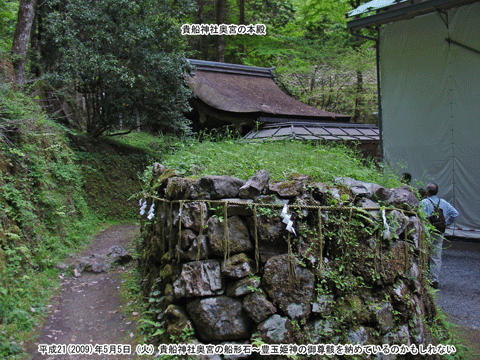
豊玉姫と玉依姫の系図
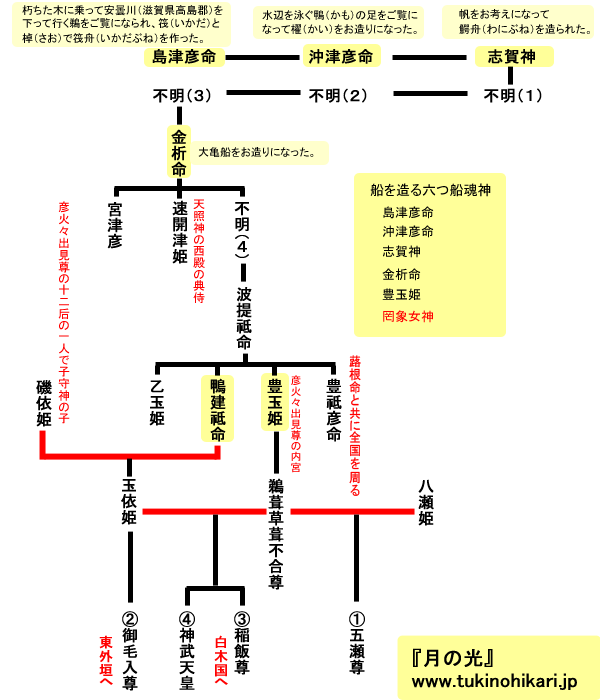
貴船神社の周辺図
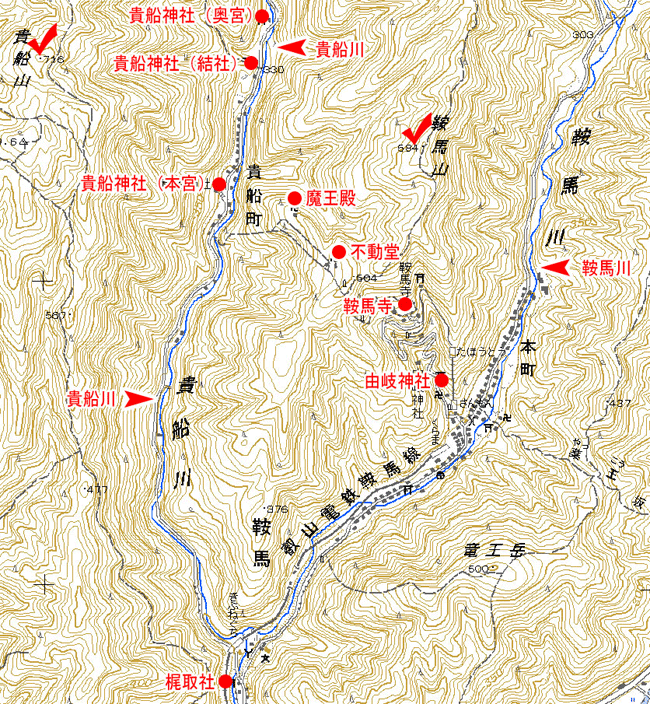
Copyright (C) 2002-2013 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
