平成21(2009)年5月5-6日(火・水)、京都市で周った神社
梶取社 | 貴船神社(本宮) | 貴船神社(奥宮)の船形石 | 貴船神社(奥宮) | 貴船神社(結社)| 鞍馬寺 | 鞍馬寺の不動堂 | 鞍馬寺の魔王殿 |
河合神社 | 下賀茂神社(賀茂御祖神社) | 出雲井於神社(いずもいのへ) | 三井神社(みつい) | 井上社(御手洗社)
| 上賀茂神社(賀茂別雷神社) | 上賀茂神社摂社の片山御子神社 | 神山(こうやま) | 深泥池(ミゾロ池) | 広沢池 |
比叡山造成の結果、穀物がたくさん出来るようになった、深泥池(みどろいけ)
比叡山造成の結果、穀物がたくさん出来るようになった、深泥池(みどろいけ)

そして、酒折の宮で木花咲耶姫に出会い、結ばれた。
翌紀元前1,290,606年に3人の子が生まれた。
紀元前1,120,703年、天之忍穂耳尊が神上がられたとき、瓊々杵尊は3年の喪祭りを行った。
喪祭りの済んだ紀元前1,120,700年、瓊々杵尊は比叡山造成の勅を出された。
比叡山造成の結果、穀物がたくさん出来るようになったのでミゾロ池(深泥池)と呼ぶようになった。

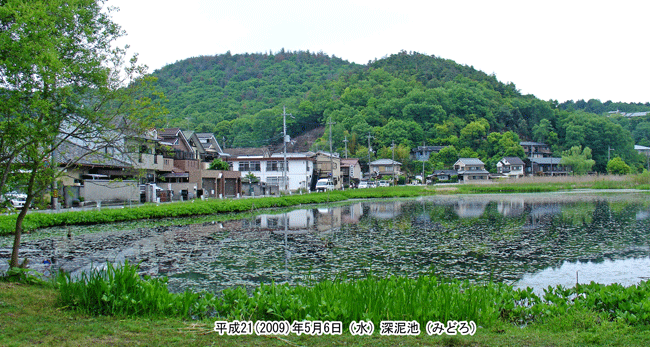
上賀茂神社(賀茂別雷神社)の葵(あおい)

雷を別け、葵葉(あおいば)と桂(かつら)によって軻遇突智神(かぐつちのかみ)と罔象女神(みずはめのかみ)をお生みになった功績から、瓊々杵尊は「別雷(わけいかづち)」という称号を天照神から賜った。
紀元前1,120,700年の比叡山造成の勅から60年経つことなく比叡山が造成されたということなので、天照神から「別雷(わけいかづち)」という称号を賜ったのは紀元前1,120,600年ごろのことだろうか?
紀元前1,120,700年の比叡山造成の勅から60年経つことなく比叡山が造成されたということなので、天照神から「別雷(わけいかづち)」という称号を賜ったのは紀元前1,120,600年ごろのことだろうか?
上賀茂神社(賀茂別雷神社)の楼門と立砂


『秀真伝(ほつまつたゑ)』の記述は、賀茂別雷神社の創祀に関わるものだろうか
『秀真伝(ほつまつたゑ)』御機の二十四「コヱ国原見山の紋」(鳥居礼編著、八幡書店、下巻P27-29 )
| 原治君(はらをきみ) | 伊豆崎宮(ゐづさきみや)に | 瓊々杵尊 |
| 箱根神(はこねかみ) | 三年祭りて | 天之忍穂耳尊を箱根神として。 |
| 瀛壺(おきつぼ)の | 峰より眺(なが)め | 瀛壺とは近江(滋賀県)のこと |
| 勅(みことのり) | 「汝(なんじ)山咋命(やまくひ) | |
| 山背(やまうしろ) | 野お堀り土お | 山背、山城は京都府南部のこと |
| こゝに上げ | 大日(おおひ)の山お | 大日山とは富士山のこと。 |
| 遷(うつ)すべし」 | 一枝(ひとゑだ)に足り | 一枝(ひとゑだ)は60年。 |
| 一枝(ひゑ)の山 | その池水(いけみず) | 比叡山 |
| 田のゾロに | 乗りて稔れば | |
| ミゾロ池 | まゝあり池の | 京都市北区上賀茂狭間町の深泥池(みどろいけ)のこと |
| 西岩屋(にしいわや) | 実(み)食(は)む礫(ゐしな)お | |
| 稜威(ゐつ)別(わ)けて | 流す石川(ゐしかわ) | |
| 塞(せ)き入れて | 荒地(あれわ)お生(い)けて | |
| 鳴る神お | 別(わ)けて鎮(しづ)むる | |
| 軻遇突智神(かぐつち)と | 罔象女神(みづはめ)お生(う)む |
貴船神社(奥宮)を罔象女宮といった。(PP103-105) 愛宕山の愛宕神社若宮の祭神に、雷神と軻遇突智神がいる。 |
| 葵葉(あおいば)と | 桂(かつら)に伊勢の | |
| 勅(みことのり) | 「天(あめ)は降り照り | |
| 全(まつた)きは | 雷(いかづち)別(わ)けて | |
| 神(かみ)を生(う)む | これ国常立尊(とこたち)の | |
| 新(さら)の稜威(ゐづ) | 別雷(わけいかづち)の | |
| 天君(あまきみ)」と | 璽(をしで)賜(たま)わる | |
| 広沢お | 太田命(おおた)に掘らせ |
京都市右京区嵯峨広沢町に広沢池があるが何らかの関係があるか。 また、上賀茂神社(賀茂別雷神社)の東に大田神社があるが、太田命に関連するか。 |
| 国となす |
賀茂別雷神社周辺図
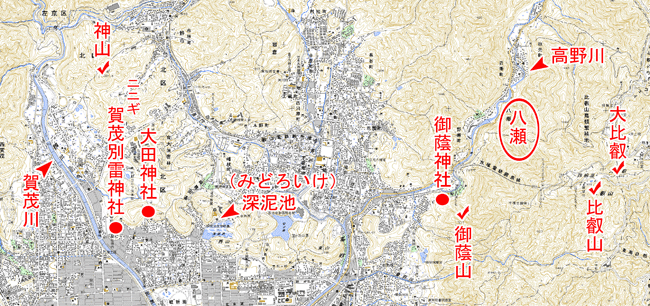
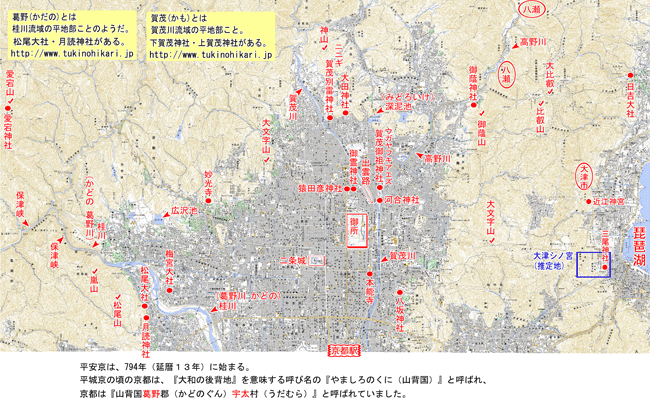
Copyright (C) 2002-2009 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。

