平成21(2009)年8月10-11日(月)、滋賀県における第二次天孫降臨の足跡、それと天之誓約の場所は・・
日置神社 | 行過天満宮(ゆきすぎ)・阿志都彌神社(あしづみ)| 志呂志神社(しろし) | 長田神社 | 大炊神社 | 白鬚神社 | 三上山 | 御上神社 |
沙沙貴神社 | 沙沙貴山 | 安土山 | 日牟礼八幡宮 | 八幡山(鶴翼山) |
沙沙貴神社(ささき)のトップページ
沙沙貴神社(ささき)

『秀真伝(ほつまつたゑ)』の〔注100〕から笹気山(ささきやま)とは・・
『秀真政伝』に「其神孫東近江の佐々木山に往玉ふ。山本に佐々木の神社ありて元祖笹気の神を祭」
とみえる。
ここにいう佐々木山とは、観音寺山の西南部の崎が細い丘になって安土町を囲むようになっている標高154メートルの山のことである。

この佐々木神社は、延喜式内社の由緒をもつ古社であり、中世近江国内で権勢を誇った近江源氏佐々木氏の氏神になったことは、史に明らかであるが、その由緒については、寒川辰清の『近江国輿地志略』所引「佐々木社記」に
「近江国蒲生郡佐々木明神者、延喜式所載沙々貴神社是也。伝称、此社祀少彦名命且奉崇仁徳天皇、今不得其縁起、則未詳其由来」
と記されているように、今日管見に入る資料の範囲内では一切不明とされている。
現在の祭神は、少彦名命・大彦命・仁徳天皇・宇多天皇・敦実親王の4座とあり、小笠原通當のいう「元祖笹気の神」である少波神とは、一見まったく無縁の社のようにもみえるが、同社の社名の表記の一つに「篠笥」とするものもあり、竹筒より笹気を造った少波神と同社の間になんらかの関連が存在し得るかもしれない。
あるいは、現在同社に少彦名神として祀られている神こそ、本来は少波神であったかもしれない。

「佐々木の神社ありて、元祖笹気の神祭後の神代に、少彦名神此宮にて和礼を教」
とあり、『秀真伝』において少波神と少彦名神は時代を異にするとはいえ、まったく無縁の神ではなかったことを記している。
後世、これが因となって、少波神と少彦名神の二神を同一神とみなす訛伝が生じるに至り、少波神の神名は忘れ去られ、あるいは同一視され、代わって、少彦名神が同社の祭神とみなされるようになったという可能性も否定しがたいように思われる。

『秀真伝(ほつまつたゑ)』の〔注99〕から笹波神(ささなみかみ)
この少波神(すくなみかみ)の賜ったササナミという神名は、近江国高島郡川上荘酒波(現在滋賀県高島市今津町酒波-さなみ )と関連するかもしれない。『高島郡誌』等の記すところによれば、当地にある旧郷社日置神社は、元酒波岩剱大菩薩と称されたとあり、酒波神(さなみかみ)との関連を推測せしめるに充分である。
ただし、祭神は素戔嗚命・日置宿禰命・稲田姫命・武甕槌命・天櫛日命・大国主命・武内宿禰・源頼道公の八柱であり、笹波神(ささなみかみ)はみられない。
また、同社の由緒に関しても『高島郡誌』には
「縁起に云ふ、腹赤ノ池に大蛇あって人民を悩ます、垂仁天皇の時素盞鳴尊稲田姫命示現あって退治し給ふ。其時の大蛇の尾より得たる剣を投げて留まりし里に岩剣の神と崇め、頭角を谷河に投げ入れ其流れ留まりし所を角山と号し角神を祀る。武内宿禰霊夢によりて社殿を創建する云々」
と記すのみである。
なお、同郡百瀬村森西(現在高島市マキノ町森西)に所在する旧村社大処神社の摂社に酒波神社(元酒波大菩薩と称されたという)があり、祭礼の際に、笹粽(ささちまき)濁酒(にごりざけ)鮒(ふな)大豆大根漬けなどを献進するのを例としたと伝えられている。あるいは、この社の方に酒波神は関連するように思われないこともないが、同書によれば、貞和5年(1349年)酒波村より勧請されたとあるので、これでは時代が新しすぎて疑問である。今しばらく断定を差し控える。
なお、酒波は、後世近江の国の一名とされ、和歌に詠まれた楽浪(佐々名実)という言葉とも関連するかもしれない。
その点、注意を要する。
沙沙貴神社の本殿

ご祭神
少彦名命大彦命
仁徳天皇
宇多天皇
敦実親王
沙沙貴神社の少彦名神

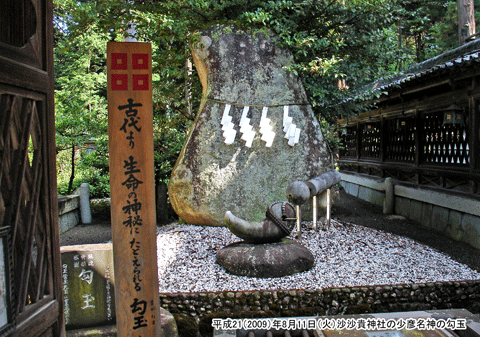

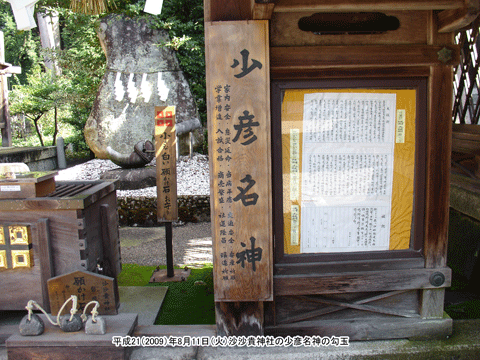
吉方之社・恵方之社
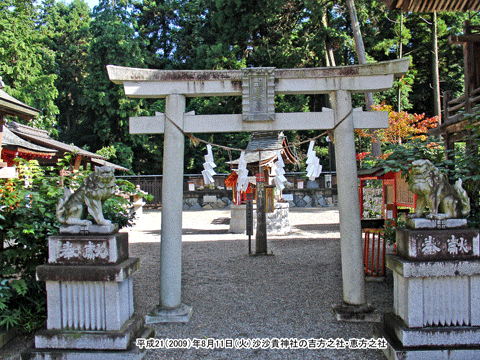
吉方之社・恵方之社

沙沙貴神社の境内図と沙沙貴神社の地図
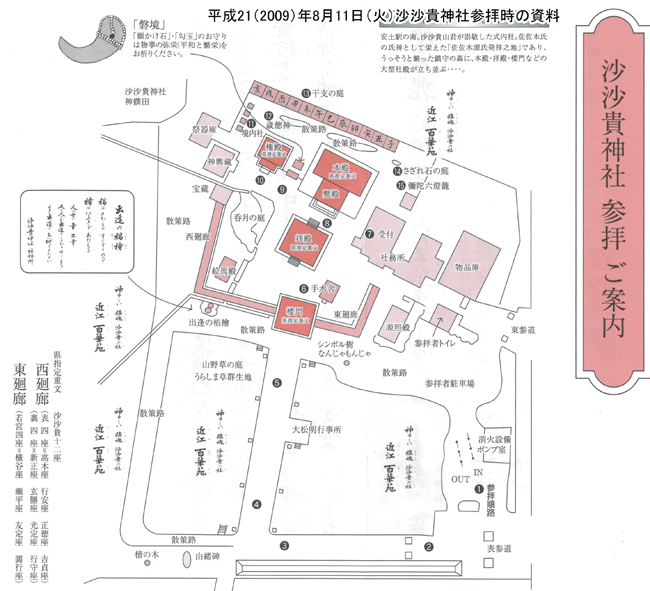
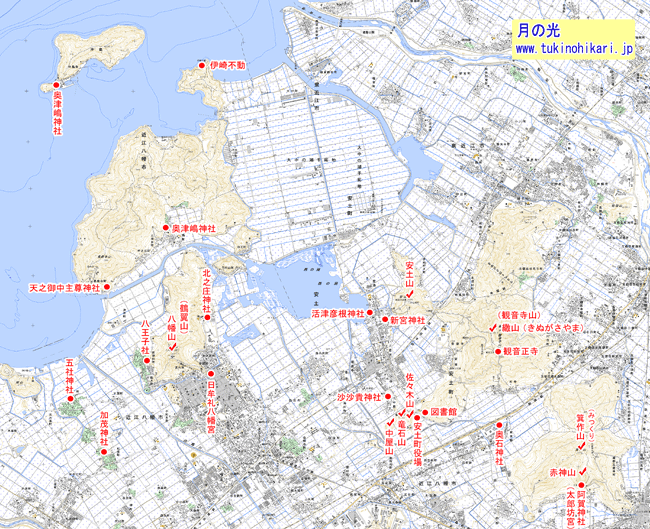
Copyright (C) 2002-2009 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
