平成21(2009)年8月10-11日(月)、滋賀県における第二次天孫降臨の足跡、それと天之誓約の場所は・・
日置神社 | 行過天満宮(ゆきすぎ)・阿志都彌神社(あしづみ)| 志呂志神社(しろし) | 長田神社 | 大炊神社 | 白鬚神社 | 三上山 | 御上神社 |
沙沙貴神社 | 沙沙貴山 | 安土山 | 日牟礼八幡宮 | 八幡山(鶴翼山) |
紀元前1,290,607年、瓊々杵尊の第二次天孫降臨の時に三上山を造成
紀元前1,290,607年、瓊々杵尊の第二次天孫降臨の時に三上山を造成

「以前日読みの宮にて、梅の花の下、三種の神宝を天照神より賜り、めでたく門出をした。
そしてまた、この白山にて梅の花の下ウケステ女の峰輿を得て、宴を張っている。これはきっと天意に叶った印である」
とおっしゃって、梅の小枝を折り頭にかざして、近江の国の高島に至りました。
その地の酒波(ささなみ)という場所に咲いていた桜の花も美しいとして、君はまたその小枝を折りかざしたのでした。
子守神の生まれた郷である高島の万木村(よろきむら)周辺を田にしようと、子守神の子、太田命と箕島命が井戸や運河を掘って、あたりに水を引きました。
日置神社から琵琶湖西岸を進んできて、鴨川を越えた志呂志神社(しろし)あたりで、大炊神社のある音玉川の淵で寝そべっている猿田彦命を見つける。
瓊々杵尊のご一行が音玉川(おとたまがわ)にさしかかると、その川の岸の白砂で昼寝をしている地元の神に会いました。
身の丈は普通の人の2倍の17咫(た)もあり、顔は赤く、鼻の高さは7枳(き)もありました。
瞳は鏡のごとく爛々と輝いていたので、君のお伴の八十物部たちが恐れてしまいました。そこで瓊々杵尊は、鈿女命(うずめのみこと)に、
「汝、あの大きな目に負けぬよう、どのような神であるか問うてみよ」
とお命じになりました。
鈿女命は胸元を開いて、裳の紐を下げて嘲り笑って、その地元の神の前を通りすぎました。
すると今まで寝ていた赤面の神は目を覚まし、鈿女命の奇妙な姿を見るなり、
「そのようなことをするのは、なにゆえか」
と申しました。そこで、
「天孫瓊々杵尊の行幸なさる道をふさぐのは何者ぞ」
と鈿女命も負けじと問い返しました。
「天照神の御孫が行幸され、この地に向かわれていると聞き、鵜川(うかわ)の仮屋(かりや)にて御饗をしてのち、この河原にてお待ちしていたのじゃ。かくいうわれは、長田(ながた)の猿田彦と申す」
鈿女命は再び、
「どちらの方から行くのだ」
猿田彦命答えて
「われがお導きしましょう」
「汝はわが君の行く先を知っておるというのか」
「君は筑紫の国の高千穂の峰に行かれる。私は途中までお伴し、伊勢の南長田川まで行こうと思う」
こう返事をしました。
それをお聞きになった瓊々杵尊はお喜びになり、あたりに咲いていた卯の花を取りかざして行かれたのでした。
猿田彦命をして、険しい山の岩石を打ち砕かせ、神の力を示すような道を開き、鎧崎(よろいざき)に至り、三尾(みお)の高い山や、鏡山の土を積み上げた三上山(近江富士ともいう)を築かせました。さらに井堰もなり水田もできたので、瓊々杵尊は猿田彦命のその功績をお褒めになり、三尾の神という名をお与えになりました。さらに猿田彦命がお気に入りの鈿女命までも賜り、猿部という名を表わし、お神楽の祖の鈿女命と並び、神楽男子の君のもととなったのでした。
瓊々杵尊は、
「三尾を開拓し瑞穂の成る水田をなし民を潤した、これこそ世の政事の鏡となることであろう」
とおっしゃって、仮宮を瑞穂の宮と名付けられました。

三上山の登山マップ
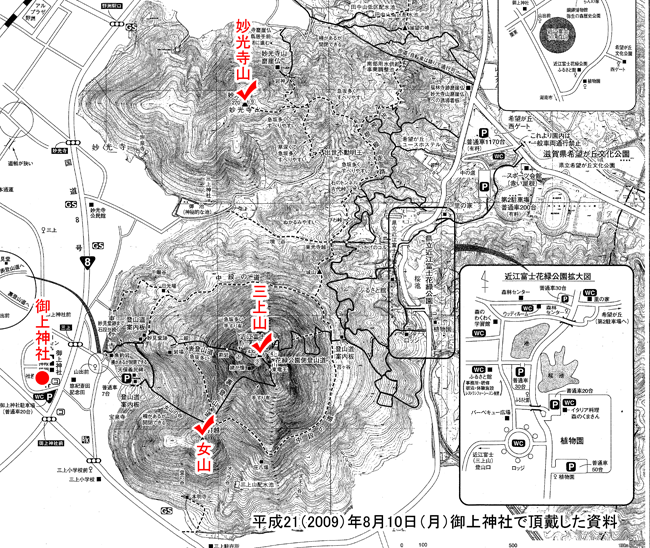
三上山からは生駒山(奈良県)と安土山を望める
三上山からは第一次天孫降臨の舞台となった生駒山が望める。
天照大神と素戔嗚命の天之誓約に関連がありそうな沖島を望むことができる。
しかも火の国の中心を象徴する安土山を望むことができる。
紀元前1,290,607年、瓊々杵尊は絶妙なポイントに三上山を造成されたのだろう。
天照大神と素戔嗚命の天之誓約に関連がありそうな沖島を望むことができる。
しかも火の国の中心を象徴する安土山を望むことができる。
紀元前1,290,607年、瓊々杵尊は絶妙なポイントに三上山を造成されたのだろう。
三上山(みかみやま)の地図
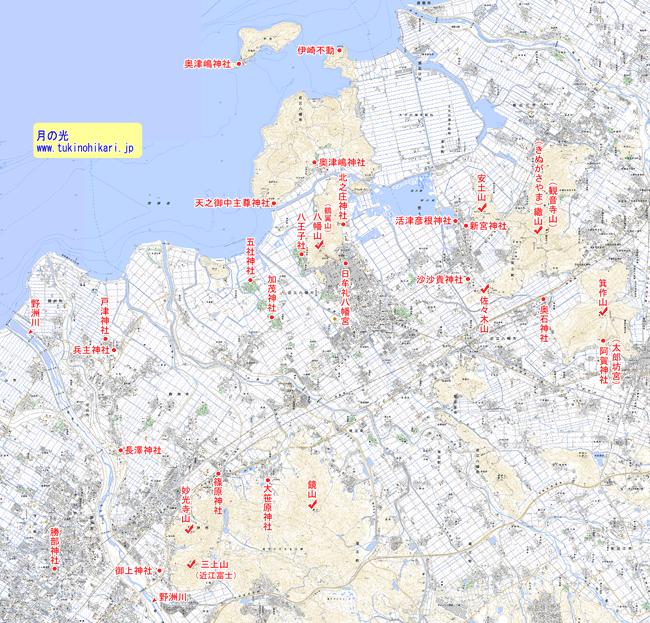
Copyright (C) 2002-2009 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
