八岐大蛇を退治後、斐伊神社で安潟神として祀ったのだろうか
平成17(2005)年8月8日(月曜日)の参拝は須佐神社から
須佐神社 | 三屋神社 | 八本杉 | 妙見山 | 斐伊神社 | 天が淵八岐大蛇を退治後、斐伊神社で安潟神として祀ったのだろうか
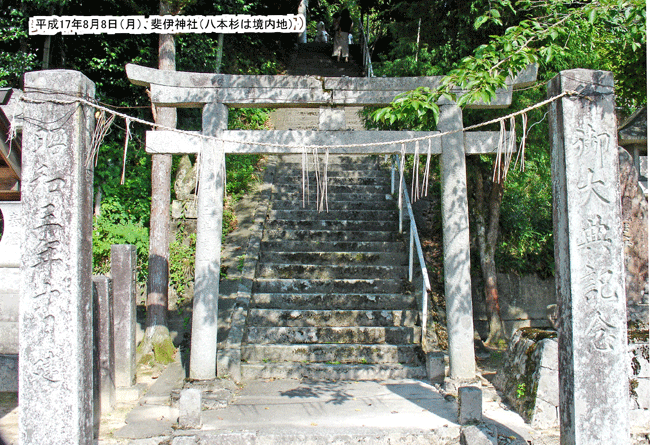
斐伊神社の祭神は須佐之男命・稲田姫命・伊都之尾羽張命である。
木次町に伝承されている八岐大蛇退治の物語の深さからすれば、須佐之男命・稲田姫命が祀られているのは極めて自然なことだ。しかし、伊都之尾羽張命が祀られているところに、もう一つ奥の伝承が隠れているような気がする。
斐伊川の北側に「引那伎」という地名が残されており、さらに南側に「伊弉冊」という地名が残されている点からみて、伊弉諾尊と伊弉冊尊の時代に、伊弉諾尊が軻遇突智尊を斬った天之尾羽張、伊都之尾羽張と呼ばれた「十拳の剱」を祀った場所だったのかもしれない。
伊都之尾羽張と呼ばれた伊弉諾尊の「十拳の剱」という八岐大蛇に先行する因縁に引き寄せられて、八岐大蛇の早子と九頭龍の持子はこの斐伊川流域にやってきたのかもしれない。
『秀真伝(ほつまつたゑ)』は、素盞鳴命は八岐大蛇を退治した後、安潟神として祀ったとしている。
素盞鳴命が八岐大蛇を退治した後、安潟神として祀ったのはこの斐伊神社においてではなかっただろうか。八岐大蛇を祀るという風習のため、木次町には八岐大蛇伝承が色濃く残されたのだろう。

『秀真伝』(八幡書店刊、鳥居礼編著)下巻「御機の二十八」より PP189-191
| 大己貴命 | 一姫お娶る | 一姫とは竹子姫(田紀理姫)のこと |
| 子の島津大人 | 三つ姫祭る | 三つ姫とは宗像3女神の竹子姫(田紀理姫)・湍子姫(江ノ島姫・多岐津姫)・田奈子姫(市杵島姫)のこと |
| 外が浜 | 厭(いと)う安潟 |
三つ姫を外が浜に厭(いと)う安潟神として祭る。 青森市に善知鳥(うとう)神社がある。善知鳥(うとう)は青森市の鳥に指定されている。母鳥が「うとう」と呼ぶと、子鳥は「やすかた」と答える。猟師が母鳥の声をまねて子鳥を呼び出し捕える、と母鳥は空にあって血の涙を流したという。 |
| 神の御食 | 食む厭(うと)うあり | |
| 九頭の | 大蛇が食めば | 青森市に善知鳥(うとう)神社の周辺に八岐大蛇の姉である持子の九頭龍が潜んでいた。 |
| 島津大人 | 羽々矢斬り振れば | 島津大人とは宗像3女神の長女・竹子姫の子。 |
| 逃げ至り | 越の洞穴 |
善知鳥神社(うとう〜青森県青森市)周辺から九頭龍は逃げ出し、能生白山神社(のうはくさん〜新潟県糸魚川市)周辺に至り、関山神社(新潟県妙高市)を通り、戸隠に逃げ延びた。この由縁により、戸隠神社ガ九頭龍の頭で、関山神社(新潟県妙高市)が九頭龍の胴で、能生白山神社(のうはくさん〜新潟県糸魚川市)が九頭龍の尻尾であるといわれるようになった。 (※)月の光>新潟県の奴奈川神社と弥彦神社 |
| 掘り抜けて | 信濃に出れば | |
| これお告ぐ | 伊勢の戸隠命 | |
| 馳せ帰り | 「汝は恐る | 戸隠命は伊勢の天照神の元で勅使をしている。 |
| これ如何」 | 答えて「昔 | |
| 二人大蛇 | 姫に生まれて | 持子が姉で、早子が妹。八岐大蛇は、早子と生まれて、宗像三女神(竹子姫・湍子姫・田奈子姫)を生み、九頭龍は姉の持子と生れて、菩卑命を生む。 |
| 君召せば | 持子は御子生み |
九頭龍の持子が生んだのは菩卑命。 九頭龍は自分の犯した罪の中でも、子の菩卑命を案じたのだ。 これは青森市の善知鳥(うとう)の伝承から読み取れるかもしれない。 母鳥が「うとう」と呼ぶと、子鳥は「やすかた」と答える。猟師が母鳥の声をまねて子鳥を呼び出し捕える、と母鳥は空にあって血の涙を流したという。 |
| 典侍(すけ)となる | 早子は姫生み | 宗像三女神(竹子姫・湍子姫・田奈子姫)は八岐大蛇の化身であった早子の罪を祓うべく、日本各地を周った。その名残が、日本各地に残る弁財天社である。 |
| 内局(うちつぼね) | 内(うち)瀬織津姫が | |
| 御后(みきさき)に | なるお持子が | |
| 殺さんと | 妬めば早子は | |
| 君お強い | 弟君請えど | ここの君は素戔嗚命のこと。 |
| 顕はれて | ともに流浪ふ | |
| 赤土命が | 女お弟君に | 速吸姫のこと。 |
| 因むおば | 早子が大蛇に | |
| 噛み殺す | 弟足名椎命が | |
| 女お請ゑば | 七姫までは | |
| 噛み食らふ | 時に素戔嗚尊 | |
| これお斬り | 身を安潟と |
八岐大蛇の化身であった早子は素戔嗚尊に退治された。 そして、安潟神として祀った。 今から160万年前のことだ。 |
| 祭るゆえ | また大山祗命の | |
| 娘と生まれ | 妹お妬む | 八岐大蛇は磐長姫と転生した。 |
| 罪の鳥 | また持子大蛇 | 九頭龍のこと |
| 瀬織津姫お | 噛まん噛まんと | |
| 百五十万穂 | 蝦夷白竜(えぞしらたつ)の |
九頭龍は150万年もの間、瀬織津姫を噛み殺そうと、蝦夷白竜の岳に潜んでいた。 八岐大蛇が退治されたのは今から160万年前の出来事だから、九頭龍が戸隠の宮に留まったのは、今から10万年前の出来事だろう。 |
| 岳に待つ | 今神となる | |
| 空しさよ」 | 戸隠命曰く | |
| 「汝今 | 日三の炎お | 九頭龍の化身であった持子は、戸隠命に諭される。 |
| 断つべしぞ | わが御食食みて | |
| 下に居れ | 祥禍身お守れば | |
| 罪消えて | また人なるぞ | 「汝持子よ、日に三度の炎の苦しみを断つべきであるぞ。わが神饌を食み、戸隠宮に慎み居れ。わが身の善悪を知り、善を守ればやがて罪は消えうせるであろう。また人と生れることもできようぞ。大蛇の緒を切るべし」 |
| 緒お切れば | 万のヲタウの | |
| 山ぞハコザキ」 |
斐伊神社の本殿
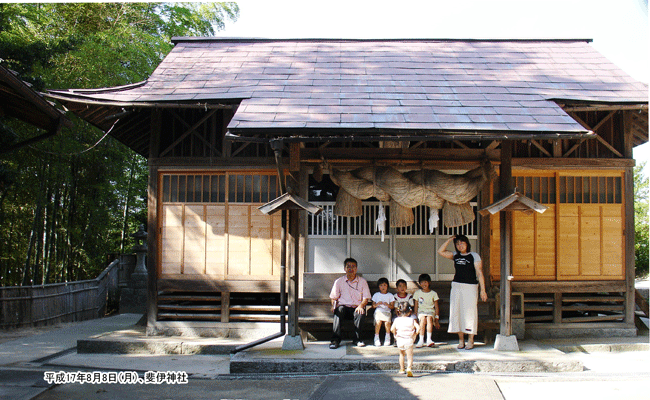
ご祭神
須佐之男命稲田姫命
伊都之尾羽張命
(合殿)樋速夜比古神社(祭神:樋速夜比古命)
摂社の火守神社
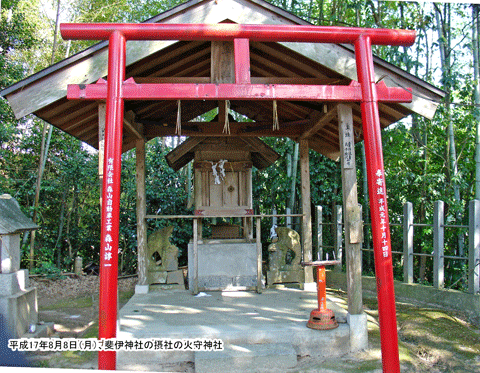
ご祭神
迦具土命摂社の日宮八幡神社
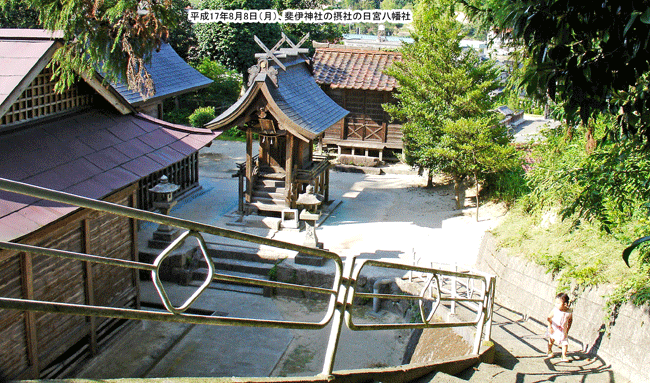
斐伊川の八岐大蛇の伝承地の地図
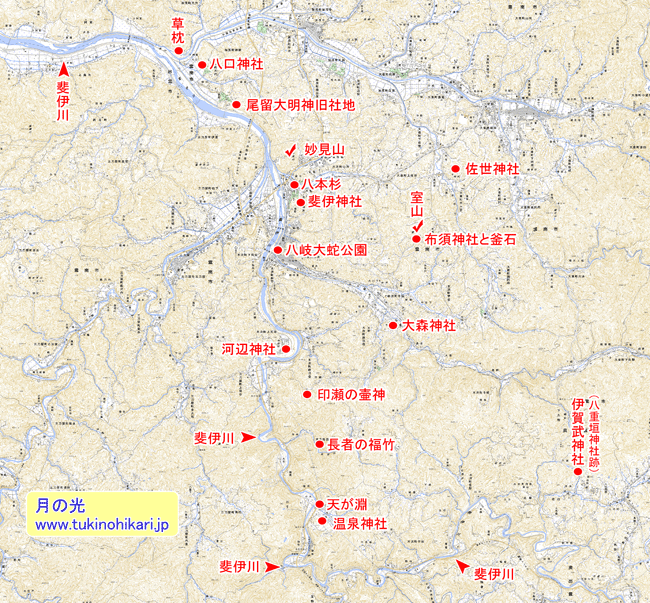
斐伊川の八岐大蛇の伝承地
| 船通山 |
島根県仁多郡奥出雲町竹崎( → 「いつもNAVI」 ) 素盞嗚命、天照大神との天誓約の後に鳥髪の峯に降臨したと伝えられる。 |
| 八岐大蛇公園 |
雲南市木次町新市( → 「いつもNAVI」 ) 素盞嗚命は天照大神との天誓約の後に鳥髪の峯に降臨。 その後、斐伊川の上流から箸が流れてくるのを見つけ、川上に人が住んでいることを悟ったといわれています。 この箸を見つけ、拾った場所が木次町新市の地であったと伝えられ、公園内に素盞嗚命と八岐大蛇が対決した場面を再現した石像と、「箸拾いの碑」が建立されています。 |
| 温泉神社(おんせんじんじゃ) |
雲南市木次町湯村1060( → 「いつもNAVI」 ) 天が淵の近くにある万歳山(ばんざいさん)に櫛稲田姫の両親、アシナヅチ、テナヅチが住んでいたといわれ、この山腹にあった二人を祀る神岩が、現在、温泉神社の境内に安置されています。 |
| 長者の福竹 |
雲南市木次町西日登( → 「いつもNAVI」 ) アシナヅチ、テナヅチと奇稲田姫は、八岐大蛇の危害から逃れるとき、この地に立ち寄り休憩されました。 使っていた竹の杖を地面に立てたところ、杖から根が出たことから「長者の福竹」という地名になったといわれています。 また、登った山の峰は「伴昇峰(ばんしょうがみね)」と呼ばれています。 |
| 天が淵 |
島根県雲南市木次町湯村1599( → 「いつもNAVI」 ) 斐伊川上流、木次町と吉田町境にある天が淵に八岐大蛇が潜んでいたといわれています。 |
|
室山(みむろやま)の 釜石(かまいし) |
雲南市木次町寺領( → 「いつもNAVI」 ) 室山(みむろやま)には素盞嗚命と櫛稲田姫を祀る布須神社(ふすじんじゃ)があります。 その麓にある岩は「釜石」といわれ、素盞嗚命が八岐大蛇の退治のときに「八塩折の酒(やしおおりのさけ)」を作らせた釜跡であると伝えられます。 |
|
印瀬の壷神 (いんぜのつぼがみ) |
雲南市木次町西日登1524-1( → 「いつもNAVI」 ) 印瀬の八口神社(やくちじんじゃ)の境内にある壷はスサノオノミコトがオロチ退治の時に「八塩折の酒(やしおおりのさけ)」を入れた八つの壷のうちの一つと伝えられ、「壷神さん」として祀られています。 この壺には「昔壷に触れたところ、俄かに天がかきくもり、山は鳴動して止まず、八本の幣と八品の供物を献じ、神に祈ってようやく静まった。」という伝承も残ります。 |
| 草枕 |
雲南市加茂町神原( → 「いつもNAVI」 ) 斐伊川と赤川の合流点に近いところに位置する草枕山は、八塩折の酒(やしおおりのさけ)を飲んだ八岐大蛇が苦しんで枕にして寝た山であるといわれています。 赤川は安政年間まで草枕山を迂回して斐伊川に注いでいましたが、度重なる水難のため山を真二つに切り開き流れを変え、現在に至っています。 |
| 八口神社 |
雲南市加茂町神原98( → 「いつもNAVI」 ) スサノオノミコトは草枕山に近い「八口神社」から矢を射て、ヤマタノオロチを仕留めたと伝えられています。 |
|
尾留大明神旧社地 (おどめだいみょうじんきゅうしゃち) |
雲南市加茂町三代( → 「いつもNAVI」 ) 素盞嗚命は、この地で八岐大蛇の尾を開いて「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」を得られたと伝えられています。 「天叢雲剣」は、またの名を「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」ともいわれ、三種の神器の一つとして熱田神宮(名古屋市)の御神体として祀られています。 |
| 八本杉 |
島根県雲南市木次町里方477-9( → 「いつもNAVI」 ) 素盞嗚命が八岐大蛇を退治した後、その八つの頭を埋め、その上に八本の杉を植えたと伝えられます。 この杉は、長い年月の間、斐伊川の氾濫によって幾度も流失しましたが、その度に捕植され、現在の杉は明治6年(1873年)に植えられたものといわれています。 |
| 斐伊神社 |
島根県雲南市木次町里方字宮崎463( → 「いつもNAVI」 ) 八本杉は当斐伊神社の境内地だったといいます。 |
| 佐世神社(させじんじゃ) |
雲南市大東町下佐世1202( → 「いつもNAVI」 ) 八岐大蛇を退治した素盞嗚命が、佐世の木(ツツジ科の植物)の葉を頭に挿して踊っている時に、その枝が地に落ちたことから「佐世」という地名になったと伝えられています。 佐世神社には、その枝が成長したといわれるシイの巨木が残ります。 |
| 大森神社(おおもりじんじゃ) |
雲南市木次町東日登1345( → 「いつもNAVI」 ) 素盞嗚命が八岐大蛇を退治して櫛稲田姫を救い、結婚の約束をして須賀の地へ向かう途中、大森の地にしばし宿られ、婚儀の準備をされたといわれています。 |
| 須我神社 |
雲南市大東町須賀260( → 「いつもNAVI」 ) 素盞嗚命が八岐大蛇を退治し、櫛稲田姫を伴なって八雲山(やくもやま)の麓に至ったとき、 「我此地に来て、我が御心すがすがし」 といわれたことから、この地域を須賀(すが)というようになったと伝えられます。 須我神社は、素盞嗚命、櫛稲田姫が造ったとされる「日本初之宮」です。 この宮を包むようにして美しい雲が立ち上がるのを見て、素盞嗚命が 「八雲立つ 出雲八重垣妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を」 と歌を詠んだことから、須賀の地は和歌発祥の地ともいわれています。 |
| 河辺神社(かわべじんじゃ) |
雲南市木次町上熊谷1462-1( → 「いつもNAVI」 ) 素盞嗚命の妻、櫛稲田姫が懐妊されたとき、産湯に使う良い水を探し求めたところ、「甚く久麻久麻志枳谷なり(いたくくまくましきたになり)」と仰せられ、河辺神社を御産所に定められたといわれています。 「久麻久麻志枳谷」は奥まった静かできれいな谷という意味であり、これから熊谷(くまたに)という地名がついたといわれ、「熊谷(くまがい)さん」と呼ばれる産湯に使う水を汲んだ井戸の跡も残されています。 |
船通山の地図
平成22(2010)年6月1日(火)から平成22(2010)年6月6日(日)にかけて【地図】船通山の地図を整理していて気づいたことは次の3つ。〔1〕船通山の北側が斐伊川(島根県)の源流にあたる「鳥上の滝」、南側が鳥取県の日野川。
斐伊川(島根県)は八岐大蛇の伝承地を通って宍道湖の西岸から注ぐ。
日野川は淡道之穂之三別島の「根」にあたりそうな場所から美保湾に注ぐ。
ひらがなで書くと「ひい」川と「ひの」川となるので相似的な関係にあるのかもしれないと思う。
〔2〕八岐大蛇の伝承地は斐伊川の東岸に集中していて、西岸にはない。
斐伊川の西岸は清浄な地という認識があった感じだ。
〔3〕斐伊川の南に「伊弉冊」という地名があり、斐伊川の北側に「引那伎」という地名が残る。
伊弉諾尊と伊弉冊尊の伝承が地名として残されている。
すごい地帯だと思う。
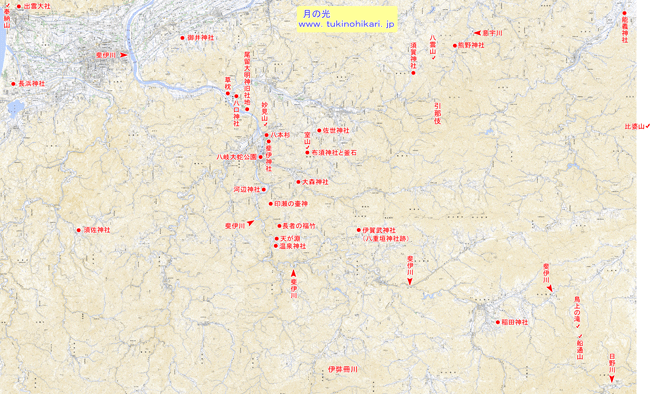
Copyright (C) 2002-2010 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
