三種神宝の分離祭祀が始まった第10代祟神天皇の御世の史跡を中心に
史貴御県坐神社 | 第10代崇神天皇の磯城瑞籬宮碑 | 大神神社の摂社の檜原神社| 第11代垂仁天皇の珠城宮碑 | 穴師坐兵主神社(通称・大兵主神社) | 相撲神社 | 第12代景行天皇の纒向日代宮碑 |
大和神社 | 大和神社の摂社の高龗神社 | 渟名城入姫神社
| 第10代 祟神天皇陵 | 第12代 景行天皇陵 | 狭井河之上顕彰碑 |
三輪山登山
大神神社 | 天皇社 | 神坐日向社(みわにいますひむかい)| 狭井神社 | 三輪山山頂の高宮神社(こうのみや) | 高宮神社(こうのみや)の東にある三輪山山頂の奥津磐座 |
史貴御県坐神社〜第10代崇神天皇「磯城瑞籬宮伝承地碑」がある トップページ
史貴御県坐神社〜第10代崇神天皇「磯城瑞籬宮伝承地碑」がある
史貴御県坐神社の拝殿

史貴御県坐神社の本殿
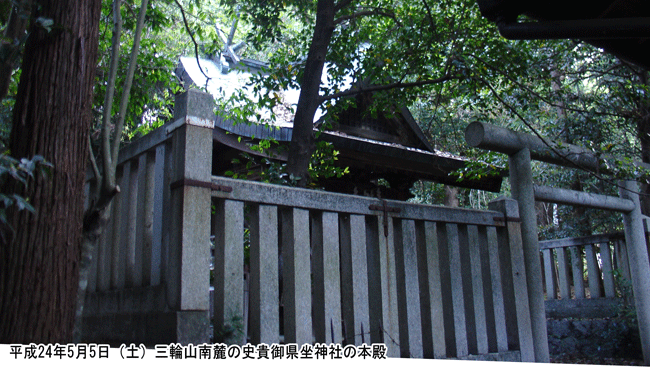
ご祭神
大己貴命(参考)
天津饒速日命『神道大辞典』
御県の霊『大和志料』
史貴御県坐神社の西側の摂社

史貴御県坐神社の東側の摂社跡
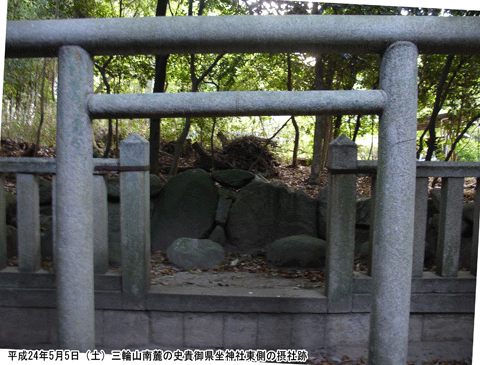
第10代崇神天皇の磯城瑞籬宮伝承地(しきのみずかきのみや)推定地
史貴御県坐神社の拝殿の前の庭の西側に、「第10代崇神天皇の磯城瑞籬宮の跡地であることを示す石標」が建っている。
三輪山周辺地図・大和三山と三輪山の地図

三輪山周辺地図・大和三山と三輪山の地図
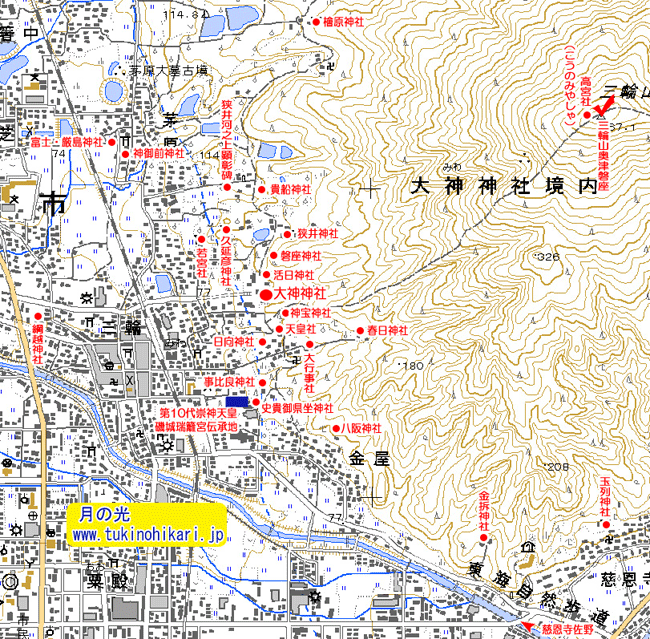
『秀真伝(ほつまつたゑ)』御機の二十九〔武仁大和討ちの紋〕(鳥居礼編著、八幡書店、下巻P233-237 )
| 国見(くにみ)が丘(おか)に | 国見(くにみ)が丘(おか)がどこか不明であるが、阿紀神社の南側にある「音羽山と経ヶ塚山 を望めるかぎろひの丘」に軍を駐留させ、歌を歌わせることが出来る。 | |
| 軍(いくさ)立(た)て | 作(つく)る御歌(みうた)に | |
| 神風(かんかぜ)の | 伊勢(いせ)の海(うみ)なる | |
| 古(いにしえ)の | 八重(やえ)這(は)ひ求(もと)む | |
| 細螺(しただみ)の | 吾子(あこ)よよ吾子(あこ)よ |
「細螺(しただみ)」は、ニシキウズガイ科の巻貝。そろばん玉の形をし、高さ2センチくらい。肉は食用。キサゴは古名。 ここでは、「下民」と「細螺(しただみ)」を掛けている。 古え、千暗の罪を免れ下民となって各地を彷徨していた素戔嗚尊のこと。 |
| 細螺(しただみ)の | い這(は)ひ求(もと)めり | |
| 討(う)ちてし止(や)まん | ||
| この歌(うた)お | 諸(もろ)が歌(うた)えば | 音羽山と経ヶ塚山に向けて、「かぎろひの丘」からみんなで歌を歌った。 |
| 仇(あだ)が告(つ)ぐ | 暫(しば)し考(かんが)ふ | |
| 饒速日命(にぎはやひ) | 「流浪男(さすらを)よす」と | |
| 雄叫(おたけ)びて | また一言(ひこと)がも | |
| 「天(あめ)から」と | 軍(いくさ)お退(ひ)けば | |
| 味方(みかた)笑(ゑ)む | 十一月(ねつき)弓張(ゆみはり) | 天鈴(あすず)55年11月弓張月の日 |
| 磯城彦(しぎひこ)お | 雉子(きぎす)に召(め)せど | |
| 兄(あに)は来(こ)ず | また遣(や)る八咫(やた)の | |
| 烏(からす)鳴(な)き | 「天神(あまかみ)の御子(みこ) | |
| 汝(なんじ)召(め)す | いざわいざわぞ」 | |
| 兄磯城(ゑしき)聞(き)き | 「厭(いと)うなす神(かみ) | 厭うなす神とは忌むべき神という意味で神武天皇のこと。 |
| 汚穢(をゑ)ぬとき | 仇烏(あだからす)」とて | いやな気持ちになっているとき |
| 弓(ゆみ)引(ひ)けば | 弟(おと)が屋(や)に行(ゆ)き | |
| 「君(きみ)召(め)すぞ | いざわいざわ」と | |
| 烏(からす)鳴(な)く | 弟磯城(おとしぎ)怖(お)ぢて | |
| 容(かたち)変(か)え | 「神(かみ)に厭(いと)うに | |
| われ恐(おそ)る | ゑゝ汝(なんじ)」とて | |
| 葉(は)盛(も)り饗(あ)え | まゝに至(いた)りて | |
| 「わが兄(あに)は | 仇(あだ)す」と申(もふ)す | |
| 時(とき)に君(きみ) | 問(と)えばみないふ | |
| 弟(と)に諭(さと)し | 教(をし)えても来(こ)ぬ | |
| のち討(う)つも | 良(よ)し」と高倉下命(たかくら) | |
| 弟磯城(おとしき)と | 遣(や)りて示(し)せど | |
| 受(う)けかわす | 道臣命(みちをみ)が討(う)つ | |
| 忍坂(おしさか)と | 珍彦神(うづひこ)が討(う)つ | |
| 女坂(おんなざか) | 兄磯城(ゑしき)の逃(に)げる |
『紀』に「女坂」とみえ、『日本書紀通証』に・・。 大宇陀町上宮奥付近か. |
| 梟帥(たける)ども | 悉(ふつ)く斬(き)れども |
奈良県桜井市吉備、春日神社北側の磐余邑(いわれのむら)伝承地といわれる磐余邑(いわれのむら)顕彰碑 兵が投降し磐余(いわれ)の由来となった大宇陀区岩室の皇大神社(こうたい) |
『秀真伝(ほつまつたゑ)』御機の三十〔天君都鳥の紋〕(鳥居礼編著、八幡書店、下巻P268-268 )
| 次春(つぎはる)十一日(そひか) | 天鈴59年1月11日 | |
| 勅(みことのり) | 「思(おも)えば忠(まめ)は | |
| 可美真手(うましまち) | 代々(よよ)物部(もののべ)嗣(つ)げ | |
| 道臣(みちをみ)と | 望みのままに | |
| 築坂(つきさか)と | 久米村(くめ)の地(ところ)お |
「築坂」橿原市鳥屋町あたり。 「久米村」は『倭名類聚鈔』に、高市郡久米郷と見える。今の橿原市久米町付近。 |
| 賜(たま)うなり | 珍彦(うつひこ)がこと | 「珍彦」椎根津彦命 |
| 船(ふね)と埴(はに) | 大和国造(やまとくにつこ) |
「埴」ここでは土地のこと。 神武紀元年の条には「道臣命(みちのおみ)に宅地(いへどころ)を賜ひて」とみえる。 「大和国造」『旧事紀』巻十「国造本紀」には「橿原朝御世、以椎根津彦命初為大倭国造」と記されている。 |
| 弟猾(おとうけし) | 猛田(たけだ)県主(あがたし) | 『紀』には「弟猾に猛田邑を給ふ。因りて猛田県主とす。是菟田主水部が遠祖なり」とある。「猛田」は、『日本書紀通証』では十市郡竹田村とするが、『大日本地名辞書』では、これでは地理が合わぬとして宇陀郡の地としている。 |
| 黒速(くろはや)は | 磯城(しぎ)の県主(あがたし) | 磯城の県主については『紀』に「弟磯城、名は黒速を、磯城の県主とす」とある。 |
| 天日別(あめひわけ) | 伊勢(いせ)の国造(くにつこ) | 「伊勢の国造」については、『万葉集注釈』所引『伊勢国風土記』逸文に「夫れ伊勢の国は、天御中主命の十二世の孫、天日別命の平治けし所なり。天日別命は、神倭磐余彦の天皇、彼の西の宮より此の東の洲を征ちたまひし時、天皇に随ひて(中略)此の国(伊勢)を懐け柔して、天皇に復命まをしき。天皇、大く歓びて、詔りたまひしく、『国は宜しく国神の名を取りて、伊勢ろ号けよ』とのりたまひて、即て、天日別命の封地の国と為し」とみえ、本書の記述と従来の史伝の間に著しい隔たりはない。 |
| 天田根神(あたねかみ) | 賀茂(かも)の県主(あがたし) |
本書において、賀茂の県主に任命されたと記される天田根神は、『旧事紀』巻十「国造本記」に「橿原朝御世。阿多根命為山代国造」とみえるのみで、賀茂の県主との関係については、一切伝がない。 天田根神の伝承が失われている。 |
| 勝手孫(かってまご) | 剣根(つるぎね)葛城(かつらぎ) |
剣根命は勝手神の孫。 『紀』に「復剣根といふ者を以て、葛城国造とす」とみえる。『旧事紀』巻十「国造本紀」に「橿原朝御世、以剣根命初為葛城国造」とある。 |
| 国造(くにつこ)ぞ | 八咫烏(やたがらす)孫(まご) | |
| 葛野主(かどのぬし)」 |
第10代崇神天皇の磯城瑞籬宮伝承地(しきのみずかきのみや)の周辺地図
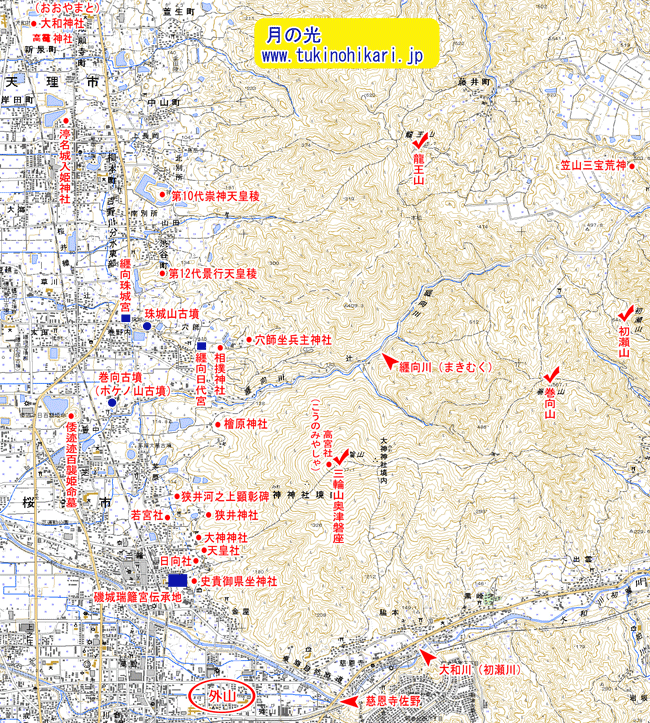
大和三山と三輪山の周辺地図
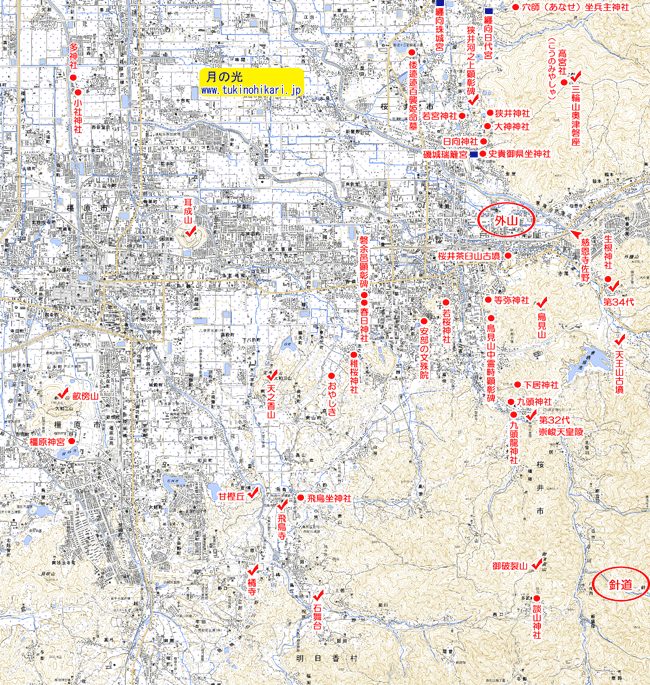
三輪山周辺地図
大和三山と三輪山の地図
Copyright (C) 2002-2012 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。

