平成21(2009)年5月3-4日(日・月)、福井県福井市で周った神社
黒龍神社(舟橋) | 柴田神社 | 藤島神社 | 天魔ヶ池 | 継体天皇の立像 | 足羽神社 | 毛谷黒龍神社足羽神社(あすわ)
拝殿


ご祭神
継体天皇 (けいたいてんのう)大宮地之霊 (おおみやどころのみたま)
【継体天皇 (けいたいてんのう)】
応神天皇五世皇孫で、越前の治水事業を行ない、平野を開き諸産業を興された男大迹王(おおとのみこ)が、この越前から第26代天皇として即位をされ発たれる時に、「末永くこの国の守り神とならん」と、自らの生き御霊を鎮めて旅立たれて行かれました。それより継体天皇が主祭神として祀られています。
【大宮地之霊 (おおみやどころのみたま)】
男大迹王が、越前でお過ごしの間に越前平野の大治水事業をされた伝承が残っていますが、その時に朝廷に祀られている大宮地之霊(坐摩神)を足羽山に勧請し、安全を祈願したのが足羽神社の起源とされています。〈別称〉坐摩神(いかすりのかみ)以下五柱神の総称
・生井神(いくいのかみ)〜井戸の神、水の神・福井神(さくいのかみ)〜井戸の神、水の神
・綱長井神(つながいのかみ)〜井戸の神、水の神
・阿須波神(あすはのかみ)〜足場の神、工事安全守神・交通安全・旅行守神
・波比岐神(はひきのかみ)〜門の神、人の出入りを守護、災難除、厄除け
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
『古事記』、『日本書紀』によると継体天皇は応神天皇5世の子孫であり、父は彦主人王である。近江国高嶋郷三尾野(現在の滋賀県高島市あたり)で誕生したが、幼い時に父を亡くしたため、母の故郷である越前国高向(たかむく、現在の福井県坂井市丸岡町高椋)で育てられて、男大迹王として5世紀末の越前地方(近江地方説もある)を統治していた。
『日本書紀』によれば、506年に武烈天皇が後嗣定めずして崩御したため大連(おおむらじ)・大伴金村らは越前に赴いて、武烈天皇とは血縁の薄い男大迹王をヤマト王権の大王に推戴した。これを承諾した王は、翌年58歳にして河内国樟葉宮(くすばのみや)において即位し、武烈天皇の姉(妹との説もある)にあたる手白香皇女(たしらかのひめみこ)を皇后とした。
継体は、ようやく即位19年後の526年、大倭(後の大和国)に都を定めることができたが、その直後に百済から請われて救援の軍を九州北部に送った。しかし新羅と結んだ磐井によって九州北部で磐井の乱が勃発して、その平定に苦心している(磐井の乱については諸説ある)。
日本書紀の記述では継体が507年に即位してから大和に都をおくまで約20年もかかっており、天皇家(実態はヤマト王権)内部もしくは地域国家間との大王位をめぐる混乱があったこと、また、継体(ヤマト王権)は九州北部の地域国家の豪族を掌握できていなかったことを示唆している。
『日本書紀』によれば、506年に武烈天皇が後嗣定めずして崩御したため大連(おおむらじ)・大伴金村らは越前に赴いて、武烈天皇とは血縁の薄い男大迹王をヤマト王権の大王に推戴した。これを承諾した王は、翌年58歳にして河内国樟葉宮(くすばのみや)において即位し、武烈天皇の姉(妹との説もある)にあたる手白香皇女(たしらかのひめみこ)を皇后とした。
継体は、ようやく即位19年後の526年、大倭(後の大和国)に都を定めることができたが、その直後に百済から請われて救援の軍を九州北部に送った。しかし新羅と結んだ磐井によって九州北部で磐井の乱が勃発して、その平定に苦心している(磐井の乱については諸説ある)。
日本書紀の記述では継体が507年に即位してから大和に都をおくまで約20年もかかっており、天皇家(実態はヤマト王権)内部もしくは地域国家間との大王位をめぐる混乱があったこと、また、継体(ヤマト王権)は九州北部の地域国家の豪族を掌握できていなかったことを示唆している。
拝殿の中
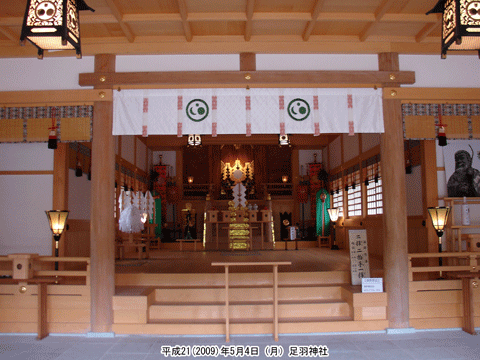
扁額
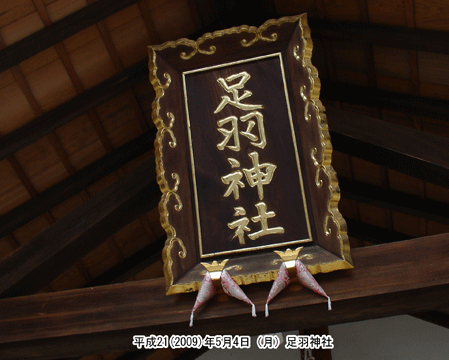
【地図】足羽山周辺図
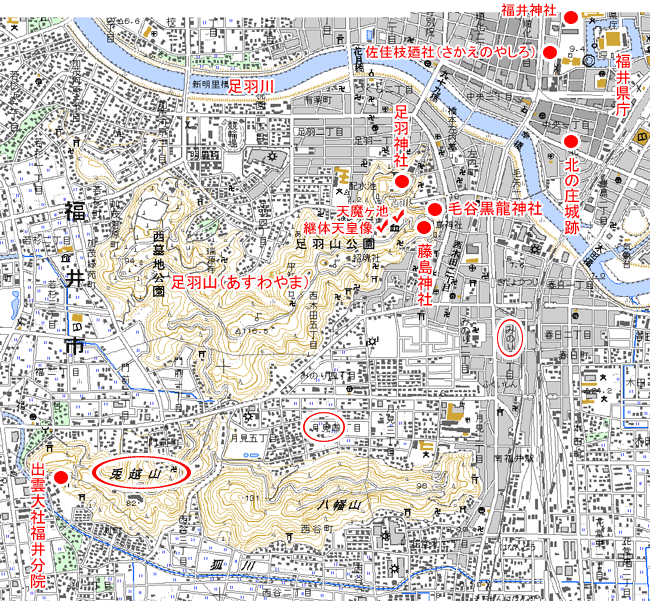
【地図】足羽山周辺
Copyright (C) 2002-2012 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
