神社に掲載されている由緒書き
神社に掲載されている由緒書き
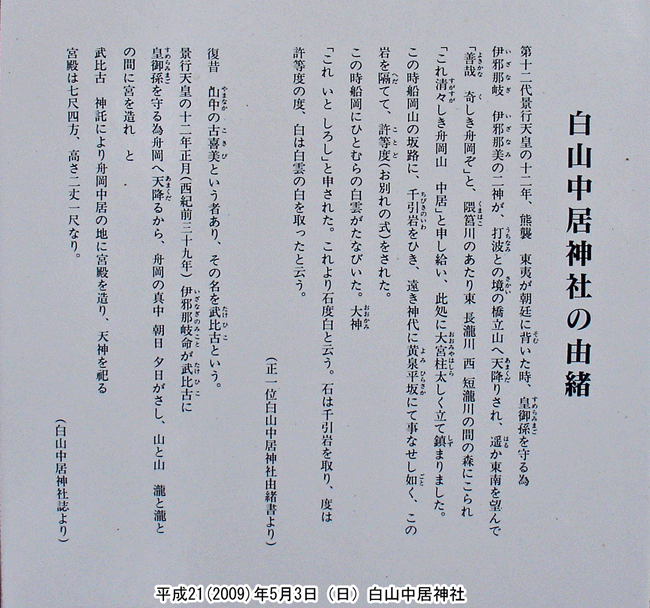
第12代景行天皇の12年、熊襲、東夷が朝廷に背いた時、皇御孫(すめみまご)を守るため、伊邪那岐・伊邪那美二神が打波(うちなみ)とも境(さかい)の橋立山(はしだてやま)へ天下(あまくだ)りされ、はるか東南を望んで
「善哉(よきかな) 奇しき舟岡(ふなおか)ぞ」
と隈筥川(くまはこがわ)東、長瀧川、西、短瀧川の間の森に来られ
「これ清々(すがすが)しき 舟岡山 中居」
と申し給い、此処に大宮柱(おおみやばしら)太しく立て鎮まりました。
この時、舟岡山の阪路に、千引岩(ちびきいわ)をひき、遠き神代に黄泉平坂(よみひらさか)にて事なせし如く、この岩を隔てて、許等度(ことど)〔お別れの式〕をされた。
このとき舟岡にひとむら白雲がたなびいた。
大神
「これいとしろし」
と申された。
これより「石度白」と云う。
石は千引岩を取り、度は許等度(ことど)の度、白は白雲の白を取ったという。
景行天皇の12年正月(紀元前39年)伊邪那岐命が武比古(たけひこ)に
皇御孫(すめみまご)を守る為舟岡に天降るから、舟岡の真中 朝日 夕日がさし 山と山 瀧と瀧との間に宮を造れ
と
武比古(たけひこ) 神託により舟岡中居の地に宮殿を造り 天神を祀る
宮殿は七尺四方 高さ2丈1尺なり。
「善哉(よきかな) 奇しき舟岡(ふなおか)ぞ」
と隈筥川(くまはこがわ)東、長瀧川、西、短瀧川の間の森に来られ
「これ清々(すがすが)しき 舟岡山 中居」
と申し給い、此処に大宮柱(おおみやばしら)太しく立て鎮まりました。
この時、舟岡山の阪路に、千引岩(ちびきいわ)をひき、遠き神代に黄泉平坂(よみひらさか)にて事なせし如く、この岩を隔てて、許等度(ことど)〔お別れの式〕をされた。
このとき舟岡にひとむら白雲がたなびいた。
大神
「これいとしろし」
と申された。
これより「石度白」と云う。
石は千引岩を取り、度は許等度(ことど)の度、白は白雲の白を取ったという。
正一位白山中居神社由緒書きより
復昔 山中(やまなか)の古喜美(こきび)という者あり、名を武比古(たけひこ)という。景行天皇の12年正月(紀元前39年)伊邪那岐命が武比古(たけひこ)に
皇御孫(すめみまご)を守る為舟岡に天降るから、舟岡の真中 朝日 夕日がさし 山と山 瀧と瀧との間に宮を造れ
と
武比古(たけひこ) 神託により舟岡中居の地に宮殿を造り 天神を祀る
宮殿は七尺四方 高さ2丈1尺なり。
白山中居神社誌より
千引岩と伝えられる磐境(いわさか)

磐境の説明書き
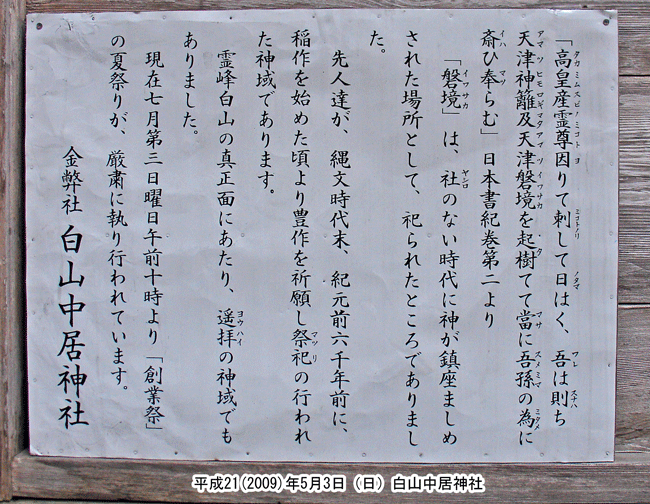
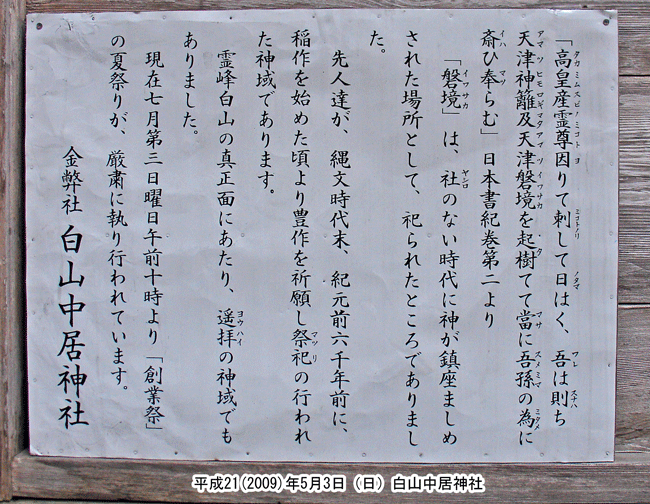
Copyright (C) 2002-2009 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
