貴船神社(奥宮)トップページ
鵜葺草葺不合尊が誕生するとき、貴船神社はすでに存在していたことが解かる。
↓
ミゾロ池
↓
葵葉と桂によって罔象女神と軻遇突智神を別ける。
貴船神社の創建は、瓊々杵尊が罔象女神と軻遇突智神を別けたことに由来するのかもしれない。
比叡山の造成↓
ミゾロ池
↓
葵葉と桂によって罔象女神と軻遇突智神を別ける。
これによって貴船神社の創祀が伺えるかもしれない。
『秀真伝(ほつまつたゑ)』御機の二十六「鵜葺草葵桂の紋」(鳥居礼編著、八幡書店、下巻P27-29 )| 君松原に | 彦火々出見尊。鵜葺草葺不合尊が生まれた敦賀湾岸の気比の松原。 | |
| 涼(すヾ)み来て | 産屋(うぶや)覗(のぞ)けば | |
| 腹這(はらば)ひに | 装(よそ)ひなければ | |
| 枢(とぼそ)引(ひ)く | 音(おと)に寝覚めて | 枢とは開き戸の、かまちの上下の端に突き出た部分。これが回転軸となって戸が開閉する。 |
| 恥(はづ)かしや | 弟(おと)建祗命(たけずみ)と | 建祗命は豊玉姫の弟で、玉依姫神の父。 |
| 六月(みなづき)の | 禊(みそぎ)してのち | |
| 産屋(うぶや)出て | 遠敷(をにふ)に至り | 福井県遠敷郡(おにゅうぐん)。滋賀県と京都府の県境をなす。 |
| 御子(みこ)抱き | 眉目(みめ)見手(みて)撫でて | |
| 「母は今 | 恥(はぢ)帰るなり | |
| 真見(まみ)ゆ折 | もがな」と捨てゝ | |
| 朽木川(くちきかわ) | 上(のぼ)り山超(やまこ)え | 滋賀県高島郡を流れる安曇川の中流を朽木川という。 |
| やゝ三日(みか) | 別雷山(わけつち)の峰(ね)の | 別雷山とは、貴船山のこと。 |
| 罔象女神(みずはめ)の | 社(やしろ)に休(やす)む | 京都市左京区貴船町に鎮座する貴船神社のこと。 |
| = 中略 = | ||
| 明(あく)る年 | 太上(おゝゑ)天皇(すべらぎ) | 皇位を退いた瓊々杵尊 |
| 別雷山(わけつち)の | 葵桂(あおいかつら)お | |
| 袖(そで)に掛(か)け | 宮(みや)に至(いた)れば | |
| 姫(ひめ)迎(むか)ふ | 時に葉(は)お持(も)ち | |
| 「これ如何(いかん)」 | 豊玉姫(とよたま)答え | |
| 「葵葉(あおいば)ぞ」 | 「またこれ如何(いかん)」 | |
| 「桂葉(かつらば)ぞ」 | 「いづれ欠(か)くるや」 | |
| 「まだ欠(か)けず」 | 「汝(なんじ)世(よ)お捨(す)て | |
| 道(みち)欠(か)くや」 | 姫(ひめ)は畏(おそ)れて | |
| = 中略 = | ||
| 姫(ひめ)は恥(はぢ) | 陥(おちい)りいわず | |
| 美穂津姫(みほつひめ) | 行幸(みゆき)送りて | 奇彦命(奇杵命の子)の妻で子守神の母 |
| こゝにあり | 問えば喜び | |
| 答え問う | 美穂津姫(みほつ)諾(うなづ)き | |
| 「太上(おゝゑ)君(きみ) | 心(こころ)な痛(いた)め | |
| 給(たま)ひぞよ | 君(きみ)と姫(ひめ)とは | |
| 日と月と | 睦(むつ)まじなさん」 | |
| 申すとき | 大君(おゝきみ)笑(ゑ)みて | |
| 建祗命(たけづみ)に | 豊玉姫(とよたま)養(た)せと | |
| 川合(かわあい)の | 国(くに)賜(たま)わりて | 賀茂御祖神社(下賀茂神社)の南側に河合神社(祭神:玉依姫神)が鎮座する。 |
| 谷(たに)お出(で)て | 室津(むろつ)に亀船(かめ)の | |
| 迎(む)い待つ | 門出(かどい)で送(おく)り | |
| 行幸(みゆき)なす |
拝殿

ご祭神
【主祭神】第2代 綏靖天皇(すいぜい)案内板

賀茂別雷神社周辺図

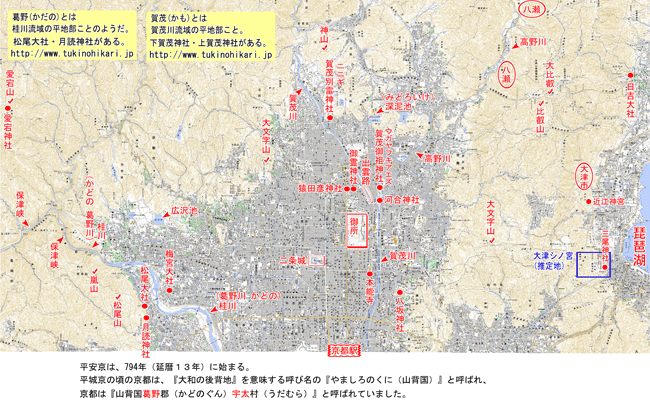
Copyright (C) 2002-2012 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.
お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
